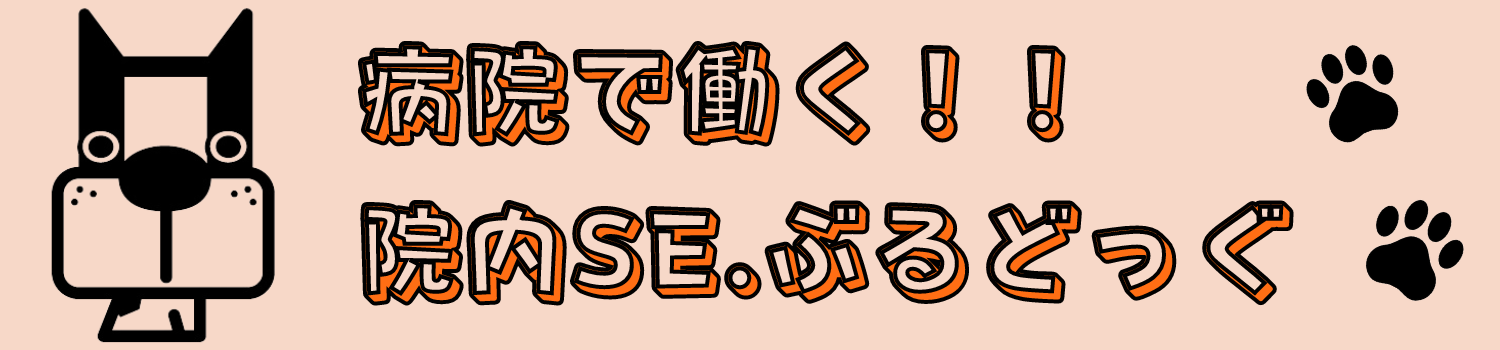院内SEに向いている人、向いていない人とは?現役SEが続けていける人の特徴を解説!

院内SEは、病院のあらゆるシステムを管理する、
目立ちはしませんが、極めて重要な業務を行っている職員です。
システムが使用できなくなると、最悪の場合病院の稼働がストップしてしまうようなこともあり得るため、システムの安定稼働は病院の運営の上でも必須です。その重要な役割を担っているのが院内SEなのです。
今回は、院内SEについて
❐ 院内SEに向いている人
❐ 院内SEに向いていない人
についてこれまでの実体験から分かったことをお伝えします。

本題に入る前に、院内SEがどんな仕事をしているのか知りたい人はこの記事を読んでみてください。
では、さっそく院内SEはどのような人が向いているのか、向いていないのかについてご紹介します。
これから院内SEを検討している人はぜひ参考にしてみて下さい。
人に何かを教えることが好きな人

院内SEはヘルプデスク業務で、システムの操作方法の問い合わせ対応を行います。
電子カルテシステムの操作方法に加えて、Word・Excel、またはPCの基本操作についても、
誰かに教える(説明する)ことが基本業務となります。
丁寧に分かりやすく説明できるかがポイントで、教える相手は年齢もバラバラで、ITの知識がほとんどない人になります。
IT系の仕事をしている人にとっては信じられないほど誰でもPCを使える環境ではありません。
「PCのデスクトップにデータを置いたので確認してください」が通じない事も普通です・・・。
そんな環境で、相手が分かるように言葉を選んで説明するのは、人によってはかなりストレスになるでしょう。
ただ、相手に理解してもらえた時は「ありがとう」と感謝されるので、いい気分にもなります。
直接感謝の言葉をかけてもらえると、やりがいを感じることができると思います。
いかに相手が理解しやすいように分かりやすく説明できるかが大事です。

★相手が理解できるまで根気強く言葉を選んで説明することが出来る人は、向いていると言えます。
★一方で、相手に上手く伝わらない時にイライラしたり、それが表情や口調に出てしまう人は向いていないと言えます。IT系経験者の人は無意識でこういう態度をとる人が結構いる気がします。「えっ。そんなことも知らないの?」の感情が相手に伝わるのは絶対にNGです。
決断・判断力、リーダーシップがある人

これを発揮しないといけない時は、「規模が大きいシステム障害が発生した時」です。
システム障害が起きた時は、ベンダーと協力して影響範囲の確認と復旧までのシナリオを仮定して
現場スタッフへ状況連絡、緊急運用を指示する必要があります。
各部署でシステム障害時の運用マニュアルを作成している事がほとんどですが、現場はバタバタになり上手くいかない所は院内SEを頼りにします。そんな時に適切な判断をして現場に指示を行う事が出来るかがポイントになります。
また各種システムの入れ替えや、制度改定に伴うシステム仕様変更時の調整など各部署へ指示を出したり、案内をしたりと先頭に立って仕切らなければならない案件もあります。

★システム障害においては、
・システムがどの範囲まで使用できるのか
・いつごろ復旧する予定なのか
・ベンダーとの作業分担をどうするか
などを素早く判断して、各現場のスタッフに伝えなければなりません。
したがって、臨機応変に対応できる力(判断力・決断力)を持っている人は、向いていると言えます。
★一方で指示を出す側として振る舞うことが苦手な人には向いていないかもしれません。
※システムは全部署に関わることなので、必然的に関わる人も多いです。
誰かを支えるポジションがいい人

病院の主役は、メディカルスタッフ(医療の国家資格保持者)です。医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師・・・・これらのスタッフ、及び、その他事務職員を含めた全職員を支える立場が院内SEです。
院内SEは病院内では目立った職種ではありませんが、いかに病院内の職員が効率よく業務ができるようにするかを日々考えながら、システムの安定稼働を守らなければならない縁の下の力持ちの存在です。

★目立たないポジションであっても、縁の下の力持ちとして誰かを支える側で仕事がしたい人にとっては、向いていると言えます。
院内SEはメディカルスタッフからいなければ困ると思われている存在なので、感謝される場面を多くてモチベーションアップに繋がります。
人と関わる事が好きな人

院内SEはヘルプデスクが基本業務になるため、「PC作業がメイン」という職種ではありません。
職員、また、外部のシステムベンダーの担当者との関わりも多くあります。色々な部署からの問い合わせを対応するため、1日の業務中で人と会話することはかなり多めです。ある意味院内で一番多くの他職種の職員と関わる機会があるとも言えます。
また、仲良くなった職員や先生から私物のパソコンについてのちょっとした相談を受けたりすることもあり、人と話す事が好きな人にとっては、やりがいを感じることが出来ると思います。

★相談を受ける側の立場になるので、話し方や雰囲気が温厚で「話しかけやすい雰囲気」の人のほうが向いていると思います。
★一方で「あまり人と会話をしたくない」「話しかけられたくない」という雰囲気を出してしまう人や、自身もコミュニケーションを苦痛に感じる人は、向いていないと言えます。
話を聞くのが上手な人

システムのトラブル時、仕様変更の依頼など会話の中で、詳しく聞き出す「ヒアリング能力」も大事な一つです。
病院職員は基本的にITに詳しくない人がほとんどなので、相手が伝えたいことを理解出来て、相手が分かりやすいように話す事が出来るかがポイントとなります。
依頼する側はどうしても内容が抽象的になりがちなので、いかに具体的なイメージを捉えて相手と共有できるかが認識相違が起こらないポイントとなります。特にシステムトラブル時の状況確認はこの「聞き出す能力」がかなり重要です。

★相手の話を丁寧に聞いて上手く会話ができる人は向いていると思います。
★一方であまり人の話を聞かずに、自分の言いたいことだけを言ってしまうような人は向いていません。
機械モノを扱うことに慣れている人

院内SEが問い合わせ関連で対応する機器は、PCだけとは限りません。
サーバーなどの大型機器や、複合機、スキャナ、タブレット端末、ネットワーク機器、モニタなど多岐に渡ります。
故障した物を修理は出来ませんが、設定変更や、メンテナンスはネットの情報や説明書などで調べならが対応することになります。
ネットですぐに見つかるものもあれば、なかなか情報がない時には業者に問い合わせをして対応していくようなこともあります。このように機械モノを扱うことが多く、機器トラブルは院内SEが何とかしてくれると思っている職員も多いです。

★説明書やネットで調べて、設定作業や対応を行うことが得意な人は向いていると思います。
★一方で説明書を読んでもなかなか理解できずに、時間がかかってしまうような人は向いていないと思います。
積極的に勉強できる人

院内SEは病院内で働くシステムエンジニアです。関わる人は全て医療従事者です。
もちろん医療用語が飛び交いますし、メインで管理する電子カルてシステムも医療の知識が必要になります。
したがって、システムエンジニアだからITの知識だけがあれば良いといった職種ではありません。
医師・看護師からのシステムの要望をヒアリングする際には、話の中の医療用語を理解していないといけませんし、
それを理解した上での提案が必要となります。

★勉強する努力を惜しまずに積極的に自己研鑽を行える人は向いていると思います。
★一方で日々勉強したくない、自己研鑽を行う時間がなかなか取れない人は向いていないと思います。
言いたいことをはっきり言える人

システムを管理する責任者として、不具合は絶対に許してはいけません。
特にほぼ全職員が使用する電子カルテについては、常に安定稼働が求められます。
時には、システムベンダーのミスにより障害が発生することがありますが、きちんと指摘を行い再発防止をさせることが必要です。対応が遅い、ミスが多いなど対応のクオリティによっては強め(激怒)に言わざるをえない状況もあります。
また、システム・機器・設備投入の業者との交渉についても業務の一つです。見積もり内容について、できる限り金額を抑えるような交渉力が必要です。

★病院のため、自分の責任として言いたいことをはっきり言える人は向いていると思います。
★性格的に強く言うことが苦手や躊躇してしまう人はあまり向いていないと思います。
以上、院内SEに向いている人・向いていない人がどのような人かについて紹介しました。
院内SEは色々な職種の人と関わるため、コミュニケーションが得意な人にとっては、活躍できる場が多いと思います。特に各部署の役職者と良い関係を築ければ色々な面で仕事もしやすい環境となります。
院内SEへの転職について気になる方はこちらの記事を読んでみてください。
 ぶるどっぐ
ぶるどっぐ院内SEは、なかなか知られていない職種ではありますが、病院にいなくてはならない存在です。
今回紹介した内容で向いている人にとっては、やりがいを感じる職業だと思います。院内SEの一番のポイントはコミュニケーション能力のため、人を相手にする仕事がしたい人にはおすすめです。
この内容がご覧の方々の有益な情報になると嬉しいです。
では、また!